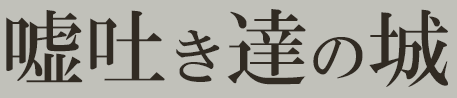何のために人は嘘を吐くのだろう。
割れた窓に地を覆う埃、剥がれた壁紙、剥き出し鉄骨。その風景は今の私の心そのまま。廃墟に私の姿は溶け込んでいるはずだ。膝を抱えて縮こまった、私の姿。
いつも落ち込んだことがあるとここに来ている。この町唯一の見所、黒の塔。黒いから黒の塔。安直なネーミング。三階より上が焼けていて、伸びた鉄骨が空にその身を晒している。天井は二階までしかない。人が踏み入っていいのは一階まで。この町には言い伝えが多い。そのうちの一つによると、この塔は巨大な雷――雷撃が落ちて今の姿になったという。
そして私は今回も、ここに来ている。落ち込んだからだ。そこまでの経緯は少しややこしい。まず、私には三人の友達がいる。男二人と美少女一人。男の片方、ケンゴが美少女ナナカと晴れて結ばれた。両思いだったのだ。私はとても喜んだ。残りの一人、テツことテツヤも喜んでいた。そこまでは良かった。しかし私はその後、こんな事実を知る。
テツも、ナナカが好きだったのだ。男二人と美少女一人は、三角関係だったのだ。テツの気持ちを知らずにいた私はショックを受けた。テツは黙っていただけでなく、私に嘘までついていた。好きな人なんて、いないと。事実を知って、私はテツを問い詰めた。
「どうして黙ってたのよ?」
「だってユズキ、二人からそれぞれ相談されてたじゃないか。お互いの気持ちを知ってたし、応援してた」
「知ってたらテツのことだって応援してたよ!」
「板ばさみにしたくない。それにユズキを一人取り残すみたいだし……ごめん」
「謝るな。何か惨めだ」
「ユズキこそ、好きな人とかいないわけ?」
「そういや考えたこともなかった」
「やっぱりか……」
「やっぱり?」
「ごめん」
「謝るな。とても惨めだ」
取り残された云々はさて置き、私はテツの嘘にさっくりと心をやられていた。何か刃物で切られたような。そう、それは切れ味鋭い嘘だった。
傷心の私はばつが悪そうなテツを置いて、塔へ来た。薄暗さは不気味な雰囲気を演出するけど、慣れた私には心地よくて何故だか安らぐ。
町はいつでも薄暗く、全体的にモノクロに見える。かつては呪術師が集まっていた土地だという。極めつけに黒の塔がそびえ立ってるものだから、ダークな印象が抜けない。そこで何故かテツとケンゴが立ち上がった。立ち上がり、両手にペンキの缶を提げ、壁に何やら描き始めた。
「何を始めた君達」
「え、町に彩りを」
「確かに彩りを加えているけれども!」
「男はロマンを求めるんだよ。ユズキならこの気持ちわかると思ったんだけどなぁ」
「ちょっと待てその理屈は私を男だと言ってないか?」
緩みきった笑顔で話すケンゴに私は苛立った声を上げた。そんな私をテツが宥める。いつも通りの流れだ。
「ユズキだって、この町に明るくなって欲しいだろ? だから俺もヒーラー目指してる訳だし」
呪いを解く魔術師、ヒーラー。呪術師が呪いをかける者であり、ヒーラーがそれを癒す者。テツはそのヒーラーになるのが夢であり、目下勉強中。
そんなやり取りもついこの前の話。目を閉じれば、あの時の鮮やかな色達が脳裏に浮かぶ。でも目を開けるとあるのは黒ばかり。
溜め息一つ。ぼんやりと私は、塔の管理人であるじいさんを思い浮かべていた。
じいさんは、塔の隣に昔から住んでいる。十年前までは奥さんがいたのだが、亡くなってしまった。そこからじいさんはボケたのか何なのか、怪しい言動を繰り返すようになった。
雷撃は再び訪れ、次は町を焼き尽くすだか。塔に神の子を住まわせているだか。その虚言は多岐にわたり、言い伝えというのは、もしかしたらじいさんのほら話の集合体なのではないかとすら勘繰ってしまう。昔は呪術師だったとも聞くが、それも真偽がわからない。
まったく。どいつもこいつも嘘吐きだな。肩を落とし、ため息をついていたら頭上から足音がした。え、上から!?
「お嬢さん! そこのお嬢さん!」
呼びかけられた!? 上から!? 混乱したまま声の方へ目線をやると、そこには少年がいた。立ち入れないはずの二階から伸びる、古びた階段に彼はいる。私が来てから、この塔には誰も訪れていない。だから、彼は二階から降りてきたのだ。
「ヒィィ!!」
「逃げないで! 俺怪しいものじゃないから!」
私は悲鳴を上げた。逃げ出したかったけど立ち上がれなかった。そのまま、彼と目が合った。
白の薄汚れたシャツに、これまたボロボロのズボン。その服装からは嘘のような綺麗な顔。少し伸びた茶色い髪はさらさらと輝き、目なんて澄んだ翡翠のよう。
「俺はハクト。異国から来た王子なんだ」
何を言い出しますか、あなた。確かに少し顔立ちが王子様っぽいと一瞬思った私は負けた気がする。
「ここは王子の城でねぇ……。俺はお姫様を探しているというわけだ」
どういうわけだ。
「あなたがお姫様なんですね!?」
「違います」
何だ何だ何なんだ。姫はショートウルフな髪型などしないだろう。自称王子は目を輝かせてこちらを見ている。ふと足元を見ると、左足首から鎖が伸びている。細い足首には……足枷? 丸い鉄の輪がはめられている。私の訝しげな目線はお構いなし。ハクトは階段に座る。彼は細い。貧相と呼べそうなくらい細いので、余計に足枷が痛ましい。
「会えて嬉しいよ」
「私は嬉しくない」
「俺は姫を探していたから」
「私は姫じゃない。ユズキ」
「ユズキ……ユズキっていうのか」
何故だかハクトは嬉しそうに私の名を繰り返した。あまりのマイペースっぷりにちょっと腹が立つ。
「その鎖は何よ?」
ハクトが一瞬表情を凍らせる。それから動揺したように目線を横に動かした。
「ふぁ、ファッション」
「嘘吐くな」
「う、嘘じゃないもん……」
声が震えている。翡翠の目も傷付いたようにかげっている。ある意味とてもわかりやすい奴だ。
「確かに見かけない顔ではあるね。何処から来たの? 観光?」
「異国だよ。遠い国」
こりゃ何聞いてもそこから離れないな。あんまり核心に迫ると、泣きそうになるし。
「遠い国なんだ。本当だよ? ユズキ……」
「わかったよ」
「え、わかってくれたの!? 俺はね。遠い国から来た王子なんだ」
凄く嬉しそうだな。目がキラキラ輝いている。わかりやすい奴だ。
「ハクトはあれだな。塔のじいさんみたいだな」
「え、本当!? 俺、じいちゃんに似てる?」
「おや、あんたじいさん知ってるの?」
「知ってるも何も。じいちゃんは異国から来た俺に、とても親切にしてくれるんだ!」
ハクトは熱心に語り始めた。意地が悪い私は白けてやる。
「いいんじゃないの。嘘吐き同士」
「じいちゃんは嘘吐きじゃないよ!」
「そんなにじいさん好きか」
「じいちゃん大好きだ!」
何だか必死にも思えてきた。もしかしたら私の言っているじいさんと、ハクトのじいちゃんは違う人かもしれない。もしくはそれもハクトの妄想か。
「あんたは。異国から来た王子で。ここは王子の城で。お姫様募集中」
「そうだよ」
「想像力豊か過ぎるな」
何で見知らぬ自称王子と会話してるんだ、私は。嘘はもうたくさんなのに。ハクトの放つ大量の嘘がギリギリと私を痛めつける。地に足もつかず、意味もなく、これっぽちも現実味がなく。切れ味は悪くて、傷口は沁みるように痛い。
言うなれば、さびついた嘘。
「ユズキはお姫様なんでしょ?」
「姫ってガラに見えるか? 私が」
「見えないけど、お姫様なんでしょ?」
「さらっと失礼なこと言わないでもらえるだろうか」
勝手に妄想繰り広げるのは自由だけど、こっちに嘘で切りつけてくるのはやめていただきたい。私は立ち上がり、ハクトに背を向ける。
「え、あの、怒らないで! お姫様っぽくないけど、ユズキは俺のお姫様なんだ!」
失礼無礼な発言に苛立っているのではないのだよ。そんなこと言ったって、ハクトに通じる気がしない。
「行かないで行かないで……置いてかないで……明日も来て!」
涙声が背中に刺さる。無視して何歩か進んだけど、結局振り返ってしまった。ハクトは膝を抱えて縮こまり、組んだ腕に顔を埋めていた。
「……お腹空いたよぅ……」
振り返らなかったら、聞き逃していたかもしれない。先程までのふわふわした声ではなかった。泣きそうでも、嬉しそうでもない、重い呟き。
あまり立ち止まっていたら、顔を上げてしまうかも。私は足早に塔を出た。
……どいつもこいつも嘘吐きだな。
* * *
さびついた嘘には、中毒性でもあるのだろうか。断じて違うと言いたい。逃げ帰ってからも、ハクトの呟きが頭から離れなかったのだ。
テツやケンゴは、食べ盛りだからか常に腹を空かせている。そんな飢えた野郎共に、私とナナカはいつも餌付けしている。でもハクトはどうだ。誰があの変人奇人に餌付けなどするか。
あんなに痩せて……食わせてやらなきゃ可哀想だろ。
「ユズキ! 来てくれたんだ!」
それ故私は今日も塔へ来てしまい、
「え、これ……くれるの!?」
サンドイッチを餌付けしてしまった。
ハクトはサンドイッチを貪り食っている。必死に口に詰め込み、とても幸せそうに頬張り、目には涙を浮かべている。
「美味しいよぅ美味しいよぅ……もぐもぐ……こんなに美味しいもの久しぶりに食べたよぅ! ……もぐもぐ」
食べる合間に感激の言葉を何度も何度も呟いている。
私はサンドイッチが大好きなので、それだけは得意なのだ。私がサンドイッチを作り、ナナカが豪華なおかずを作る。こうして四人、お弁当を持って遊んだこともあったな。
嬉しそうに食べているハクトを見ていると、私は友達三人を思い出さずにはいられない。
胸が、痛んだ。切れ味鋭い嘘につけられた傷が、再び痛み出す。
「ユズキ、あのね。王子はね。十七歳の誕生日に、呪われちゃうんだ……。でも、お姫様が王子を救ってくれるんだ!」
胸が痛んでいるのに、コイツはまた嘘で切りつけてくる。しかも、さびついた嘘。
「……誕生日いつよ」
「今日! 今日なんだよ! ユズキ、王子を助けてくれよ!」
さびついた嘘につけられたたくさんの傷が、ヒリヒリ沁みる。痛いんだよ。嘘はすっごい痛いんだよ。嘘はもう嫌なんだよ……!!
「それには鍵が必要なんだ。じいちゃんの部屋にあるはず。それさえあれば王子は助かるんだ!」
寝言は寝て言え聞きたくない。空言徒言放つのやめろ。戯言吐くならその口閉じろ。
「ユズキ! 行かないで! 俺を助けて!」
私は叫ぶハクトを無視して、塔の出口へ足を進めた。食わせてやった。後は嘘吐きに用などない。
「ゆ、ゆゆユズキなんて嫌いだぁ……!」
いきなり震えるハクトの声。驚いて振り返ってしまう。
「きらっ……嫌いだもん! ユズキのばばばバカぁ、嫌いっ!」
それでもサンドイッチを手放さない。息を切らせ、目を潤ませ、動揺を全身で表現している。
おいおい。どうしたんだ。動揺がこちらにも伝染してきていたが、憤りが勝っていた。
振り切るように、私は走った。
* * *
全然垢抜けていない、小さな町。特産品は瓶詰め。人形の家のような低い建物の間を縫って走り、いつのまにか四人の隠れ家に来ていた。建てたまま誰も越してこなかったという、豪華すぎる置き土産。階段を下りれば、とても広い地下室がある。瓶詰めと缶詰が蓄えてあるから、いつでも籠もれる。私は四人の拠点に自ら飛び込んでしまった。案の定先客がいて、気まずい再会を果たしてしまった。何やら勉強していたらしいテツ。昨日会ったばかりなのに、随分と久しぶりに思える。黒くてぺたんとした髪に、猫のような吊り目。今日もヒーラーの勉強をしているのだろう。
見慣れた姿に安心したのか、全身から力が抜けた。その場にへたりこむ。誰もいないはずの塔から人が現れて、自称王子で脳内ファンタジーで、その上私に懐いてきた。平静を保とうとしていたけど、私の容量はとっくにオーバーしていたらしい。
何処から来たんだ。あの足枷はなんだ。あなたのおうちは何処ですか。塔なんですか。どうなんですか。
腹が立って、何だか怖くて、逃げてきてしまった。ハクトはどうなった。今頃泣いているのか。何者なんだよ……ハクト。
「ユズキどうしたの!?」
テツが駆け寄ってくる。
もう、全部夢なんだ。全部全部何かの嘘なんだ。きっと。
* * *
テツと並んで座っている。しばしの間の後、テツがぽつり話し始めた。
「嘘吐いて、本当にごめん。何ていうか……現実に耐えられなかった。嘘吐いて逃げてた」
落ち着いた声に私の傷が癒えていくようだった。でも一つ、引っかかる言葉があった。
――現実に耐えられなかった。
「テツ。私、塔でね。嘘吐き王子に会った」
一言声を発したら、とめどなく言葉が溢れ出した。私は堰を切ったように塔での出来事をテツに話した。
頷いて相槌を打ちつつ、黙って聞いていたテツ。表情が強張っていた。私の話が終わると、テツはまた静かな声で話し始めた。
「ウチのばあちゃんが、塔のばあさんと仲が良かったんだ。だからみんなが知らない話も俺は知ってるんだけど……」
塔のばあさんは大人しくて、あまり交友関係は広くなかった。そういえば私もばあさんのことはよく知らないかもしれない。
「塔のばあさん、孫がいたんだ。そのお孫さん、本当の孫じゃないらしくて。そのお孫さんも、ばあさんが亡くなってから見かけなくなったって」
ばあさんが亡くなった頃、私達は幼かった。お孫さんに関する記憶は全くない。
「お孫さん、塔に捨てられてた子供らしい。何処から来たのか、誰の子なのか、わからない。じいさんばあさんに拾われてからも、家に籠もってたって」
だから余計に記憶がないのか。
「ここで、次の話だ。この数日、じいさんが新たなほら話を始めた。いつもより大声で、叫んで町中回っている。『神の子を捧ぐ時が来た』。ユズキ、俺が何を考えてるかわかる?」
塔に住まう神の子。ボケたじいさん。姿を消した孫。じいさん大好きハクト。おうちは塔。足枷。かつての呪術師。呪われる王子。……神の子は捧げられる。
「嘘だ……。ばあさんが亡くなってからってどんだけの期間よ。そんなに長い間、ハクトは一人で塔に閉じ込められてたって訳?」
「そうじゃなきゃ、結局ハクトって何者だと考えられる?」
異国から来た王子。塔は王子の城。お姫様を探している。
お姫様は、王子を呪いから救う。
「ユズキ!! 何処行くの!?」
私はまた駆け出していた。さっきの言葉が脳内で鳴り響いている。
――現実に耐えられなかった。
* * *
塔の二階の部屋には鍵がかけられていた。中からではないと開かないらしい。
「ハクト!! ユズキだ!!」
ドンドンとドアを叩き、大声を張り上げたけど反応も物音も何もない。この部屋にハクトはいない。ま、まさか既に「捧げられ」てる? ど、どうしよう。どう動くか。そうだ。「じいさんの部屋にある鍵」だ。私はまた走り出す。
じいさんの小さな家に、勝手ながらお邪魔させてもらう。戸締り用心。中を漁るのはさすがに躊躇われたが、鍵はあっけなく見つかった。テーブルのど真ん中に、見事に目立つよう置かれていた。鍵をつかむ。さて……ハクトは何処だ? 鍵を手にしたら、開けるしかない。鍵がかかっている場所……取り敢えず二階の部屋だな。
二階の部屋はこの鍵で開いた。住める程度の廃墟部屋。たくさんの本棚、中には童話が並んでいる。その童話はいくつか無造作に積まれ、隅には質素なベッド。そして、足枷を留めるための鉄球。――嘘吐き王子はここで誕生した。鉄球を眺めても、繋がれているはずの鎖が見つからない。外されている。部屋を見回す。入り口と向かい合った壁際に階段を見つけて、駆け下りた。
階段は地下まで伸びていた。ここにもあった。広い地下室。ようやく、ハクトを見つけた。うずくまるように横たわり、足枷はまた別の鉄球に繋がれている。私は歩み寄っていく。綺麗な顔の表情は空っぽだった。翡翠の目の奥が寂しそうに、怯えたようにうっすら光っている。残り少ないハクトの感情の灯。嘘や強がりという鎧を着ていない。
本当の、ハクト。
よく見たら、左手の皮膚に錆みたいなのが浮かんでいる。そして弱っている様子。……本当に呪われてるのか。これ。
「ゆ、ユズキ……?」
「助けに来た。さ、とっとと逃げるぞ」
まさかと思いながらも鎖に鍵を差し込んだら、外れた。同じ錠前かよ。私は腕をつかんでハクトが立つのを手伝う。
「ユズキ、いつも塔に来てたでしょ。俺、ずっと話したいと思ってたんだ。城に訪れたお姫様。名前はユズキ。王子は姫の助けで城を出るんだ」
何とか立ったハクトを、今度は歩かせる。重い足枷をずっとつけていた左足は上手く動いてくれないようだ。
「ずっとずっと、そうだったらいいなって……」
私はハクトの目を見れず、前を向いたまま支えて歩いていた。何とか階段の前まで来た。
「何をしている」
嗄声が地下室に響く。隣の部屋からじいさんが登場した。異様なオーラをまとったじいさんの手が挙がり、私に黒い光が放たれた。目を閉じる――そして強く押される感触。
目を開けると、しゃがみこむハクトがいた。私を、庇ったのだ。黒い光がかすった部分のシャツが焼けていた。
「ユズキ。早く逃げて」
「何言ってんだ……私はアンタを助けに来たんだ!」
ハクトは私の足を押す。じいさんは近寄ってくる。
「じいちゃん、俺、要らない子だよね――今日は俺が、捨てられた日」
親に捨てられて、ここでもじいさんに……そんなことあってたまるか。でも、どうしたらいい。万事休す、か。黒い光が再び飛んでくる。
しかし、光は私達に当たらなかった。後ろから現れた透明な壁が、防いでくれた。振り返ると、そこにはテツがいた。追ってきてくれていた。ヒーラーは呪いを治すことに加え、防ぐこともできる。テツは素早くハクトを背負った。
「ユズキ、行くよ」
私達は階段を駆け上がる。塔の出口へと急ぐ。
「今日が誕生日なのは、じいちゃんと出会った日だから」
ハクトは、一貫してじいさんを恨まない。何をされても。ハクトからさびついた嘘が剥がれていく。
私達は、塔を出た。ハクトがぽつり呟いた。
「――空だ」
じいさんも遅れて塔の外へ出た。ハクトと目が合い、その瞬間じいさんは咆哮し、崩れ落ちた。異様なオーラが消えていった。
それが嘘吐き達の、終焉だった。
* * *
じいさんは、昔のような穏やかな人に戻った。ばあさんが亡くなった時に何者かが憑き、ハクトが塔を出て憑物が落ちたらしい。呪術師には時折あることだという。
ハクトはテツの元で看病された。テツはたくさんの本を読みながら、ハクトにかけられた呪いを見事に解いた。ハクトは元気を取り戻し、じいさんと二人、家で暮らしている。
私達四人に仲間が増えた。ハクトだ。今は五人で仲良く遊んでいる。
町はカラフルに彩られ、その虹色は新しい風を待っているようだった。
黒の塔は城でなくなり、姫を待つ王子も姿を消した。
もう、嘘吐きはいない。
さびついた嘘は、空へと消えた。