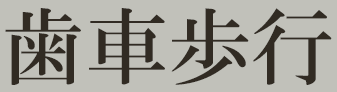――意志を自身に告げた時、歯車は廻り始める――
「何でだっ!? どうやって抜け出すことができた!? あの扉は……? 何故開いた?」
白む空が夜明けを知らせる。群青が街にその青を落としている。
大きな道の両脇に、高い建築物が立ち並ぶ。建物に見下ろされたような道の真ん中には、路面列車の線路が敷かれている。
その道をよぼつきながら歩き、叫び、時折壁にもたれかかれるようにして立つ男。今、この道にはその男しかいない。
男は次の言葉を繋いだ。目線は定まらず、瞳は淀んでいた。
「何だよ。電話も出ない。メールも返さない。どういうことだよ……!?」
男は項垂れ、膝と手を地面についた。そして呻くように声を漏らした。言葉にはなっていなかった。
やがて男はゆらりと立ち上がり、また道を歩き始める。すると道の端に、少女の姿を見つけた。
少女は押し殺したように泣いていた。しゃがみ込み、顔を腕の中に埋めて。
男は少女の元へと歩み寄る。先程とは打って変わった優しい表情を顔に浮かべて。
「どうされました?」
少女は涙に濡れた顔を上げ、かけられた優しい声に救いを求めて目を静かに輝かせた。
「初めまして。何かお助けできることはありますか?」
男はしゃがんで少女に目線を合わせ、人の良い笑顔で微笑んだ。
建物の奥にひっそりと、それでいて荘厳に建っている時計塔。
午前四時。街中に鐘の音が響き渡った。
* * *
この時計塔は確か二百年程前からあったものだそうで、今も時を刻んでいる。正午と午後六時には、鐘もなる。
その中には部屋がいくつかあり、時計塔は一つの家とも呼べる。その一室が私の住む部屋だ。
私の住んでいる部屋の入り口は、歯車が複雑に絡んだ構成になっている。扉の表面を覆いつくした歯車が、ドアノブを捻り開け閉めする度に回る。開け方も閉め方も、他の扉と変わりはない。違いは外観だけに見える。
そんなこの扉には難点もある。理由はわからないが、開かない時があるのだ。ドアノブを捻った時に回るはずの歯車が、回らないのだ。
理由はわからない。放っておいたら直ってしまう。そしてまた開かなくなる。少し前まではそれを時々繰り返していた。
しかし最近、私は外に通じるこの扉を開くことができなくなった。
そんな私もまた変わっている。まず両親が歯車の研究者で、整備士だ。この都市は歯車技術が発達している。それが色濃く表れているのが例の時計塔であり、時計塔を管理しているのも両親だ。時計塔の中は部屋も含めて大小様々な歯車がむき出しになっていて、時計や設備を動かし、時が来たら鐘を鳴らしている。
両親は今、歯車の研究のために遠くへと旅立っている。私は一人で留守番だ。
両親よりもある意味変わっているのは、私自身だろう。私の足の中には、歯車が入っている。
事故で上手く動かなくなった私の足は、義足や杖ではなくて、歯車が動きを手助けしている。歯車技術は医療にまで貢献している。
一つ残念なのは、扉の歯車と同じく、足の歯車も時折動かなくなることだ。何故だか、そちらの方も最近動かないことが増えていた。
私では開かない扉を何も問題ないように開ける彼。私と彼との関係は説明がつかない。一緒に住んでいるだけあって、友達以上ではあるのだろうが、恋人とも言い難い。ここまで仲良くなったのは最近のことだろうか。足は動かない、外にも出られないという状況を知って、最近ここに住むようになった。面倒見がとてもいいのだ。
それを表すかのような人の良い笑顔がこちらに向けられる。
「ただいま」
優しい声が部屋を震わせる。彼はこちらに歩み寄り、私の頭を撫でる。
「一人で大丈夫だった? 今から夕食の準備するから」
彼は周囲からも評判が良い。優しくて、人当たりが良い。話し方も聡明で、誰もが彼に好意を抱く。
彼は台所に立ち、手際よく仕度を始める。時折つく溜め息から、彼が少し疲れていることが伺える。私は無意識に体を強張らせた。息が詰まる。足の中の歯車が動きを鈍らせたような気がした。
着信を告げる静かなオルゴールの音。音に反応したように、壁の歯車が回り始める。回転した歯車は、どうやら電波に反応する歯車らしい。着信は私の携帯だ。私は携帯を手に取り、電話に出る。
相手は友達で、私は動いてくれた足を引きずりながらリビングを出る。部屋の中の壁は壁紙が貼られていて、歯車はあまり表に出ていない。しかし廊下というより通路のそこは、コンクリート張りになっているし、歯車も露わになっていて工場のようにも見える。
友達はたまたま退屈していたらしく、私の近況を聞きたがった。私は壁沿いに立ててある、金属製の手すりにもたれて話す。これは両親が私のために立ててくれたものだ。歯車に巻き込まれないように、と立てられた。友達の声と歯車の音が耳朶に触れる。
しばらく話して友達は、
「眠くなった」
と電話を切った。私は君の暇潰しかい、と心の中で突っ込みながら私はリビングへと戻る。
台所に立っていると思った彼は、部屋の手前の方にいて私はたじろぐ。
「ミコ、何話してたの?」
先程の声色からは想像できない、まるで脅すような口調。私はこの後の展開が、脳内で痛いほど響いた。足の歯車ががちり動きを止めるのを感じ、私は膝からがっくり崩れ落ちる。
「俺の悪口でも言ってたんだろ?」
「……言ってるわけないでしょ?」
「じゃあ、何故部屋を出て行った?」
「電話って、静かなところでするものだと思うから……」
「俺がいたらうるさかった?」
「そんなこと……」
「ほら、俺のこと悪く言ってたんだ。そうなんだ……!」
私は首を横にブルブルと振る。薄く開いた口からは途切れ途切れ息が漏れ出すだけで、声が出てこない。
「何黙ってるの? 無視してるわけ?」
違うの。声が出ないの。私は口をパクパクとさせて、意志を伝えようとするけど何も出てこない。
きっと喉まで声帯まで歯車なんだ。だからきっと動きを止めてしまったんだ。私は脳の奥でうっすらそんなことを思った。
「だから歩けなくなるんだ。お前なんか……」
心に何か大きな物が刺さった感覚がして、一瞬激しい痛みを覚える。そして全身が脱力し、私は動けなくなった。
あぁ、全身歯車だ。そして動きを止めたんだ。部屋のあちこちにある、歯車式のどの小物も動きを止めているような気がした。ところどころにある、部屋の歯車だって。もしかしたら通路の歯車も。
歯車は私の所為で動きを止めるんだ。私が悪いことをするから。私がどうしようもないから。全部あの人の言う通りなんだ。
どうしていつもいつも直せないんだろう。直しても直しても私は至らない。こんな私だから歯車は動かない。
いつも助けてくれているのに、ごめんなさい……。
視界の端の時計が夜の六時を指していたけど、いつもの鐘の音は鳴らなかった。
私はそのままその場から動けず、気がついたら意識が薄れていた。
何となく残っている記憶だと、彼が私をおぶってベッドへ運んでくれていた。はっきり目が覚めた時、ベッドにいたのだから多分そうなのだと思う。
うつらうつら現実と夢の合間を行き来した。彼の声が聞こえた。いつもの優しい声だった。
守ってあげる、と安心させるような言葉が聞こえていた。
それは、現実なのか、夢なのか。私の幻想なのか。
目が覚めたら、彼が側にいた。ベッドの枕元にいくつか置いてある、小さな時計をまじまじと眺めていた。いつもと同じように、壁と歯車が視界に入った。くすんだ金色の歯車。やはり動きが鈍いように思えた。歯車が回すものの一つに砂時計があるけど、斜めに傾いたまま止まっているように見える。砂だけは重力に従って、さらさらと落ちている。
壁にかかっている小さな歯車も目に入る。細い鎖がついていて、ネックレスになっている。
見慣れたそのネックレスに、細かい文字が書かれているのに私は気付いた。
『When you tell will to yourself, the gear begins to turn around.』
拙いながらに、訳そうと試みた。後半部分は「歯車が回り始める」だろう。やはり私は歯車という言葉に反応するようだ。では、前半は何だろう? わかりそうで、わからなかった。
「ミコ。おはよう。遅いけど夕食にしようか」
彼はいつものように微笑んだ。先程何事もなかったように。私はいつもその笑顔に安心している。している、はずなのに。何故だか今、不安を覚えた。彼はいつだって私を助けてくれている。必要で、大きな存在だ。それなのに。
心のざわめきが止まらない。これは何を意味するのだろう。
「どうしたの? 準備してくるね」
彼が私の元から離れた。私はそれを見届けて携帯を持ち、リビングを出て行った。足は何とか動いた。通路の先にある、例の開かない扉を思った。
友達に電話をかける。友達はすぐ電話に出てくれた。話したいことがある、と言うと、快く返事をくれた。さっき寝たから眠くない、そうだ。
「あのね。彼が最近怖いの。上手く言えないけど、怖いの」
「何言ってるの、大丈夫でしょ。あの人とっても優しいじゃない」
「彼と仲良くなってから、部屋のドアを開けられなくなった気がしてきたの」
「気のせいよ。気のせい。そのうちまた開けられるって」
「それに私、彼に怒られてばかりで……何だか自信とか自分を失くしている気がして……」
そこまで話しかけたところで、部屋の扉が開いた。通路に彼の姿が現れる。
「ミコ、お前何話してるんだ」
私の胸元を左手で乱暴につかんで、顔の前にぐっと引き寄せる。
「怒られてって、お前がいけないんだろう……!? 何だよその台詞」
彼は空いていた右手を振り上げ、私の頬に掌を打ちつけた。私は倒れこんだ。体を打ち付けて、全身が痛い。殴られた頬に鈍い痛みがじわじわと走る。彼は倒れこんだ私に携帯を投げつけて、再び手を振り上げた。私は手を伸ばして携帯を引き寄せ、叫ぶ。
「聞こえてる……? 助けて!! 殴られる、殴られるよ助けて!! キャーッ……」
話している間にも彼の怒号が飛び、また顔を殴られてしまう。逃げようとしたけど、こんな時なのに足はまた動かない! 私は、電話越しの友達の返答を祈るように待つ。
「助けて!! ねぇ、お願い、助けて!!」
「んー? どうかした? よく聞こえないよー。ちと面倒臭くなったわ。切るね」
友達の気だるい声が辛うじて聞こえた。
「え!? ちょっと待って!! 助けてよぉ!!」
私の叫びも虚しく、携帯からはツーツーと通信が切れたことを告げる電子音が鳴っていた。
……味方はいないんだ。私は、一人だ。誰も助けてくれないんだ。
足に意識を寄せ、動かそうと試みる。ギリギリと膝が曲がり、足に力が入って行くのを感じた。身を捩って彼から離れる。驚いた彼の隙をつき、私は遂に身を起こして、立ち上がった。
――歩け、できたら走れ、逃げるんだ。
――私を助けられるのは、私だけ。
私は足を引きずりながらも何とか全力で走り、部屋へと逃げ込む。カバンとか、目に付いたものをとにかく引っつかんだ。近くにかかっていたあのネックレスもつかむ。
彼が私を追って部屋へと入ってくる。今まで見たこともない、恐ろしい形相だった。彼が何か叫ぶ前に、私はその場にあった時計や小物を投げつけた。
「コノヤロ……」
彼が立ち上がろうとした瞬間、部屋の中の歯車が回り始めた。時計が時を刻み、傾いたままの砂時計が定位置に戻り始める。
私も彼も目を丸くし、一瞬動きを止めた。しかし私はすぐに気を取り直し、彼の隙をついて再び駆け出した。
足はどんどんスムーズに動いて歩を進めて行く。
扉は開いた。部屋を出て、時計塔の中を駆け巡る。ここは私の家のようなものだから、近道がわかる。でも、彼はわからない。だから多分、逃げられる。
遂に時計塔を出て、街へ飛び出してまたしばらく走る。激しい息切れが襲ってきて、私は走るのをやめて歩き始めた。
ゼェゼェと呼吸をしながら、私は未だ手に握っていたネックレスに目を落とした。
『When you tell will to yourself, the gear begins to turn around.』
……自分に意志を告げた時、歯車は回り始める。
英文の意味に気付いた時、私の脳は急速に回転を始めた。全ての歯車がかみ合って回り始める。
思い返すと、足と扉の歯車が動かなくなる時は、いつだって彼、あるいは他の人の言うことを聞き入れていた。
それは私のためになると思っていたけど、全てを聞き入れることは、自分を失くすことだった。
自分の意志を、私の気持ちを、失くすことだった。
私は彼が好きだった。本当に好きだった。多分彼も私を好きだった。どういう意味かまではわからないけど、きっと好きだった。
でも、今は……
カバンに括っていた腕時計を見る。彼から出た夕食という言葉から夜を連想していたが、既に夜中の三時後半だった。
私は街を歩く。行き先は全く考えてなかったけど、両親の元へ取り敢えず逃げようと思っていた。街は眠っている。建物も、路面列車も。時計塔も。暗い夜道だけど、きっともうすぐ日が昇る。
歯車は回る。私の足を動かす。
私は、私自身で歩いて行く。私と歯車で、歩いて行く。
いつしか空が綺麗な青へと色を変えていった。どこか遠くで、小鳥の鳴く声が聞こえた。
後ろを振り返ると、既に時計塔の姿は遠かった。また、帰ってこれたらいい。私の居場所なのだから。
私の意志は回る。何処かで歯車が軋む音がしたような気がした。時計塔の時計が、午前四時を指す。
鐘の音が、私の耳に届いて心地よく響いた。
さよならではなく、また会おうと言っているように。
少女が歩を進める時、世界は廻り始めた。
時計塔の鐘は、はじまりを告げた。